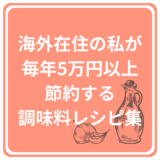調味料とは何でしょう。実は調味料にも分類があります。調味料の役割や分類を理解すると、料理がよりおいしく、楽しく、簡単になります。
なぜ調味料を使うの?
そもそも、何で調味料が必要なのでしょうか。もちろん料理を美味しくするためです。
以前の記事でも述べたように、おいしさには様々な要素があります。
その中でも、調味料がかかわってくるのは主に味と香りです。それでは、この二点に注目して、調味料を分類してみましょう。
調味料の分類
繰り返しになりますが、調味料の目的はこの2つです。
- 味を足す
- 香りを足す
そして、味は塩味、甘味、酸味、苦味、うま味の5種類から構成されています。
もちろん、嗅覚は味覚に大きな影響を与えるのですが、ここでは味と香りを分けて考えます。すると、調味料は以下の3種類に分類できます。
- 味だけを足す調味料
- 味と香りを足す調味料
- 香りを足す調味料
それでは、それぞれについて詳しく見ていきましょう。
味だけを足す調味料
まず、味だけを足す調味料を見ていきましょう。味だけを足す調味料は、言い換えれば、においのしない調味料です。具体的には、以下のような調味料があります。
- 塩味:塩
- 甘味:白砂糖(グラニュー糖、上白糖)
- 酸味:クエン酸
- 苦味:なし
- うま味:味の素、いの一番、ハイミー
たとえば白砂糖は、加熱によりカラメル化反応やメイラード反応を起こします。なので、使い方によっては苦みや香りを与えることもありますが、基本的には味のみをつける調味料です。
そして、うま味といえばだし汁を思い出す人も多いでしょう。しかし、だしの香りを簡単に思い出せるように、だしはうま味と香りの両方を与えるものす。ですから、純粋にうま味だけを足す調味料は味の素などのうま味調味料となります。
味と香りを足す調味料
次に、味と香りを足す調味料を見ていきましょう。実は、ほとんどの調味料が味と香りを足す調味料に含まれます。具体的には、以下のような調味料があります。
- 塩味:しょうゆ、みそ、ハーブ塩など
- 甘味:ブラウンシュガー、はちみつ、みりんなど
- 酸味:米酢、果実酢など
- 苦味:なし(オリーブオイル)
- うま味:だし、だしのもと、しょうゆ、みそなど
たとえば、お酢は酸味を足す調味料です。加えて、酸味の元の酢酸分子が揮発しやすいので、味と同時ににおいも感じます。
さらに、しょうゆやみそ、果実酢のように、複数の味を与えるものも存在します。
そして、苦味を与える食材は、コーヒーやチョコレートなどいくつか存在します。さらに、成分としては挙げられます。具体的な調味料は、強いて言えばオリーブオイルです。しかし、オリーブオイルを苦みを足す調味料として使う場面を考えると、パンをディップする、など非常に限られた場面です。基本的にオリーブオイルは、苦味を足す調味料としては使いません。
香りだけを足す調味料
最後に、香りだけを足す調味料を見ていきましょう。これに分類されるのは、ハーブや薬味と呼ばれるものです。
- こしょう、ハーブ類、にんにく、しそなど
もちろん、例えばしそを食べると香り以外に植物由来の味を感じます。しかし、その味はかなり弱く、料理の味付けに影響するのはほとんどが香りです。
油は味?辛みは?
厳密に味というと、塩味、甘味、酸味、苦味、うま味の5種類ですが、広義の味として、以下のことも考えておくと料理に役立ちます。
唐辛子、こしょうなど
辛味は、厳密には味覚ではなく刺激ですが、生活の中では味覚として扱われています。辛い料理、おいしいですよね。
油
油を感知する神経が味蕾に存在すると確認されています。そのため、油は第六の味になるのではないか、と言われています。
確かに、塩味しかないポテトチップスやバターなどを美味しいと感じるのは、複数の味があると美味しく感じる、という理論から外れるので、少し不思議な気もしていました。ですが、油が味として含まれるなら納得です。
なぜ分類が大切なの?
ここまで、調味料の分類について考えてきました。そもそも、なぜこれを知る必要があるのでしょうか。それは、料理の味付けの時に必要だからです。
おいしいと感じる基準は人それぞれで、万人がおいしいと感じる味は存在しません。つまり、どんなレシピでも、おいしいと感じる人とそうでない人がいるわけです。せっかくレシピ通りに料理したのにおいしくない、となった場合、調味料の分類を理解していれば、かなりリカバリーがしやすくなります。
そして、この分類を理解していれば、みりんの代用についての私の主張も、かなり理解しやすくなるはずです。
美味しさについて、こちらの本を参考にしました。味に関して疑問に思ったときは、真っ先にこの本を調べる、わたしの愛読書です。